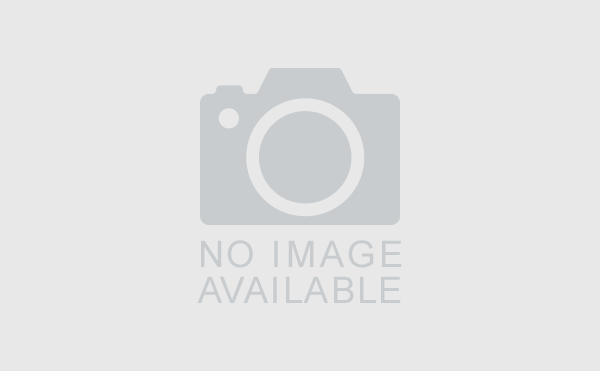OPENカンファレンス@67日目
いよいよOPENカンファレンスも2日目.
OpennessやOpen Sourceなど,大きく変化を遂げつつあるコミュニケーションの形について,様々なプレゼンテーションが行われた.
無事2日間のカンファレンスが終了したが,ちょっと気になったことがあった.
Openという考え方だが,非常に多様性があり,その言葉を捉える人のバックグラウンドによって,かなり内容に幅があるように思えたのだ.
ある人は「オープン」=「タダ」と考えていたり,またある人は「オープン」=「誰でも自由に」と考えているような印象を受けた.極端な事を言うと「今現在の悪いものや閉塞性のあるもの」のアンチテーゼとして「OPEN」を持ち出してきているような気がした.
確かに「オープン」にすることによって,多くの人に様々な機会(チャンス)を与えることができるだろう.しかしながら,そうすることで全てが万事うまくいくと考えるのは幻想であると思うのだ.
「完全に自由にする,枠をなくす,制限を撤廃する」事が,Win=Winの関係をもたらすのかというと,決してそうではない.
高校時代にとある本で読んだことがあるのだが「俳句は5・7・5の制限があるから美しい」という考えもある.
つまり,制限=悪というのは非常に偏った見方であるということだ.むしろ「OPEN」という概念は危険性もはらんでいるように思える.
例えば,すべての著作物がオープンになってしまうと,著作者はどのようにして賃金を得ればよいのか?何もかもボランティアによって成り立つことは確かに理想だが,人間が日常生活を維持するためには,働きに対しての対価を得るべきなのではないだろうか.また「責任の所在」が合間になってしまうという危惧もあるだろう.
結局のところ,今後,私たちはOpenという環境をどのように享受し,どのように使っていき,どのような社会やコミュニケーションを作っていくべきなのか?そんなテーマを今回のカンファレンスは投げかけてくれたように思える.
関係者の方々,お疲れ様でした.
で,カンファレンスの後は,打ち上げでした.
いつものところ(大学内のLUME)でワインとチーズなどでパーティーをしました.また例によって例のごとく,お酒が入ると饒舌になってしまい,日本文化の閉鎖性について議論したり,写真表現とは何かとか,雪で滑らないための方法などを話したりしました.
いつものことですが,何故お酒を飲むと(自分でいうのも何ですが)あんなに話上戸になるのかが不思議です.